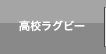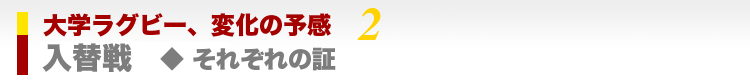
![]()
![]()
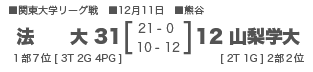
目標は一部昇格ではなく、一部復帰だ。
かつて関東リーグ戦1部にいた彼らには戻るべき場所として1部リーグがある。山梨学院は2部2位で1部との入替戦へ。対する1部7位校は、逸材ひしめく法政だった。 シーズン序盤に黒星を背負い込んで上位断念を強いられたが、高校日本代表などの経験者も多い才能集団。下手をすれば大量点差も...戦前はそう予想する向きもあった。
結果は法政の貫禄勝ち。特に、前半43分、山梨0−9法政で、法政WTB竹下がカウンターから見せた突破は、本来の能力の高さをまざまざと印象付けた。しかし、その格差は山梨学院の健闘を際立たせた。12-31。大差でもおかしくなかった試合は、挑む側がひるまず自分たちの力をぶつけて、引き締まった。
法政HB団が長いパスで構成するフィールド中央での突破力、カウンターから繰り出すバックスリーの爆発力。しかし山梨はTB陣の確実なディフェンスと安定したラインアウトで法政をなかなか自陣へ入れなかった。前半30分、法政がBKラインでゴール前に迫った時、大外に決定的場面ができた。振り回した揚句の2対1。ところが法政の一人目がボールを持ってDFの外へ仕掛けた瞬間、真っ直ぐに戻ってきていたカバーディフェンスに強烈なヒットを食らった。山梨のタックラーたちは、法政の出方に応じて巧みにボールキャリアを倒し、さらにどうやってボールを奪うかの意思統一を見せた。思い切りが良く、相手の意図がよく見えている。
ラインアウトが上手だから法政も、やみくもにはタッチに出せない。それが、法政の高速カウンターを呼び覚ますきっかけにもなったのだが。12-31の試合後の会見で、吉田浩二監督は選手を称えて、声を震わせ泣いた。「途中からエンプティ・ランプ、点きっぱなだったはずです。が、選手たちは最後まであきらめなかった。広島工業出身、松永積俊主将は、試合を振り返って赤い目で1分近くも沈黙した。「....悔しいです」。本音だったはずだ。
『昇格に足りなかったものは』『相手との実力差はどの程度あったのか』。記者の質問に答えても、彼ら自身の教訓にはなりにくい。記者の質問に答えても、彼ら自身の教訓にはなりにくい。自分たちはFWでボールを奪い、前に進め、ボールを持った相手を倒し切るのだ。それをやり切ってなお、届かなかっただけだ。彼らなら、仮にもう一度戦ったとしても、もう一度同じように挑んだに違いない。ただ涙が止まらず、語ることは特に残されていない。そんな幸せなゲームも珍しい。
![]()
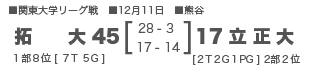
1部8位・拓大と、2部1位・立正大のカードは、「お互いの強みがだぶっていた」と拓大・遠藤監督。互いの力の差はわずかでも、局面ごとを制する側が一方的に支配して見える試合に。敗れた立正は、やはり1部所属の経験がある。堀越監督はさばさばと答えた。「最後は大学選手権を見据えたチーム作りに集結していくはず。この、法政、拓大に勝たなければ、たまたま1部昇格が果たせても先がない。まだ力不足なんです」。この80分を戦いながら、チーム作りの目線は遠くに遣っていた。
![]()
![]()
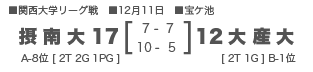

真っ向勝負を受け止め、跳ね返した摂南大。写真はLOカウバカ・コンスタンチン
「原点回帰」
入替戦が決まった直後の11月30日、監督の指示でグラウンドに掲げられたボードに はそう書かれていた。
入替戦までの2週間、練習前に毎日ボードを眺め、日々新たな気持ちで練習に取り組んだという。
「当たって、走って、燃えろ」。
同じボードに書かれた別の言葉は、技術以上に気持ちが大切なことを教えてくれた。「体張った奴が何人かしか見えへん」 同点で迎えたハーフタイムでの河瀬泰治監督の激に、後半ガチンコなタックルで答えた選手たち。 大産大のトンガ留学生コンビの再三の突破も、ひたむきなカバーディフェンスでゴールラインを割らせなかった。
後半開始から20分近くの大半を自陣で戦い耐える中で、反撃から勝ち取った追加トライ。トライ後のコンバージョンが決勝点となった。気持ちの前向きさを象徴したのはロスタイム。2点差でリードする中、ベンチからのPG指示 に対してグラウンドから返ってきた言葉は「まだ2分もあるんですよ」。 結局PGを選択し、3点を追加したが、最後まで守りに入らず、攻める姿勢を貫いていた。
![]()
![]()
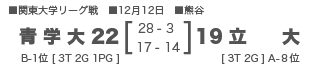

すべての局面で競り続けた青学大(左)と立大。またも死闘に
クロスゲームは約束されていた。2008年から始まった、入替戦でのこの顔合わせ。青学大がA、立大がBと、逆の立場だった'07年の対戦も含めれば4年連続だ。
歴史を振り返っても(立大側から見て24−14、20−18、24−7と)、昨季以外はいつも死闘。そして今年、Bグループで青学大が突出していた背景を考えれば、例年以上に濃密な80分となることに疑いはなかった。
今季開幕第2戦の帝京大の後半25分にLO福田がトライを奪って以来、最終戦の成蹊大戦までついに5試合連続ノートライ。3点刻みでしか得点を積み上げられず、日体大と引き分けただけの全敗だった立大。この日は、そのPGを重ねてきた1年生SO中澤を控えにまわした。司令塔には、もっとも攻撃力のある浅川を起用。ブレイクダウンの連続で地域を刻み、機を見て仕掛けて反則を誘い、ショットを狙う。シーズン当初から貫いてきた戦い方を、最後の最後に方向転換したのだから不安はあった。しかし、攻撃力のある相手を考え、「リスクをおかさないとリターン(5点=トライ)もない」。覚悟を決めてのキックオフだった。
試合は、開始直後から青学大の正確さが光る。先制トライを奪うまでの4分、ほとんどミスがない。時間をかけて築いた充実を印象づけた。
一方の立大も、9分、12分と、守本主将がトライを挙げ一度は逆転。これまで奪えなかったトライが生まれたのだから、方向転換が奏功したように見えた。しかし、ミスも多い。アタッカーが限られる。やがて強引になり、苛立つ。ブレイクダウンで2ケタほどターンオーバーしてみせ、接点のしぶとさにAで戦ってきた者の意地を見せたが、終わってみれば19−22。ゲームデザインがもう少しうまくいっていれば逆転できるところまで持っていけただけに、このスタイルが、この日から、この日だけだったことが悔やまれた。
試合後の立大・川監督は、「対抗戦の成り立ちを考えれば、どんな相手にも最善の策で勝ちにいくのが、その思想だと考えた。だから、あの(刻む)戦い方を徹底してきたが、それが選手たちに負担になったかもしれない」。こだわりが、選手たちの自由、発想、プレーの幅に、制限をかけたかもしれないことを悔やんだ。「選手たちは最後まで逃げることなく立派にやり抜いた。指導者の責任です」。
![]()
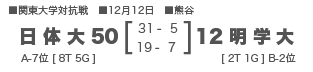

安全圏に入るまで、パワーで試合を制圧した日体大。「意地があった」
パワー全開の日体大。集中力は明学大が鋭い。そんな滑り出しだった。
早く安全圏に入りたい日体大は開始2分、モールを押し込んでFL高井が先制トライを奪う。しかし、直後に見せた明学大の攻撃が鮮やか。キックオフからBK展開するとFBが防御を裂き、WTB肥留川がトライ。その後もチャレンジャーは、ブレイクダウンへの入りで鋭く、日体大をなかなか安心させなかった。
ただ、日体大が「意地」と表現したマスト・ウインの姿勢は、時間の経過とともに明学大を押し退けた。18分、日体大は敵ゴール前のスクラムを押し込み好機を作ると、PR佐々木がトライ。25分にもスクラムから、SO植松が切れ込む。力強さで流れを制圧し、勝負を決めた。
試合後の両軍には、涙があった。日体大・米地監督は、「今日ここにいる悔しさ、今季の不甲斐なさを噛み締め、涙を流した者もいた」と話し、「意地とプライドで勝った」と言った。2年続けてAとの差を思い知らされた明学大の選手たちも、大きく肩を落とした。土佐監督は、「昨年入替戦に出場したことで、部員も28人から40人に増えた。この舞台を経験し、いろんな部内基準が上昇しています」。上を向いているからこそ落ちた涙なのだと伝わってきた。
![]()
![]()
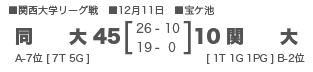

最終的には大勝も、前半は粘られた同大。関大も意地を見せた
試合後に喜びはなく、残留の安堵感もさることながら、むしろ無念さが色濃くにじむ雰囲気だった。
「最後までもたもたしてしまった」(中村直人HD)との言葉どおり、前半だけで16点差も、点差ほどの力の差を感じない戦いぶり。
横に流れるラインは、攻撃の圧力を薄め、サポートの寄りの遅さは、攻撃の厚みを感じさせない。個々の力の差からくる余裕から、結果的にトライは生まれたが、チームとしての力強さの印象は薄かった。「しんどかった。学生はもっとしんどかったと思う」試合後の囲み取材の中で、中尾晃監督は何度も何度も「しんどい」を繰り返した。 未知の経験、降格への不安、過去との葛藤、創部百年という節目への無念さなどが監督の言下に滲む。
この数年間の成績が出ない中での入替え戦出場とAリーグ残留は、新たな栄光への第一歩となるか。リーグ最終戦 と入替戦の2試合を戦い、喜べない勝利の存在と、勝つことのみに意味がある戦いを経験できたことは、チームにも個人にも大きな財産。来年以降の上昇軍団復活を関西全体が待ち望んでいる。